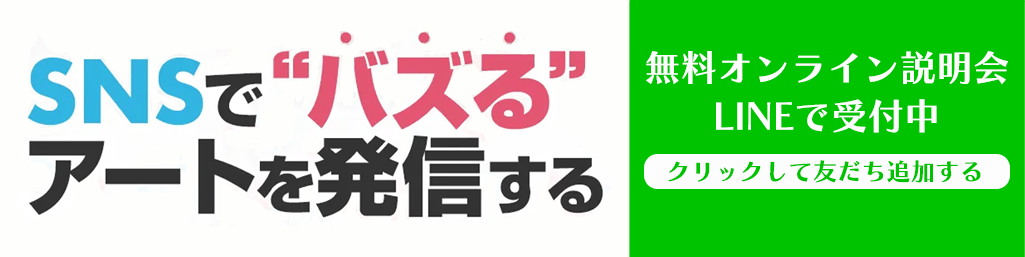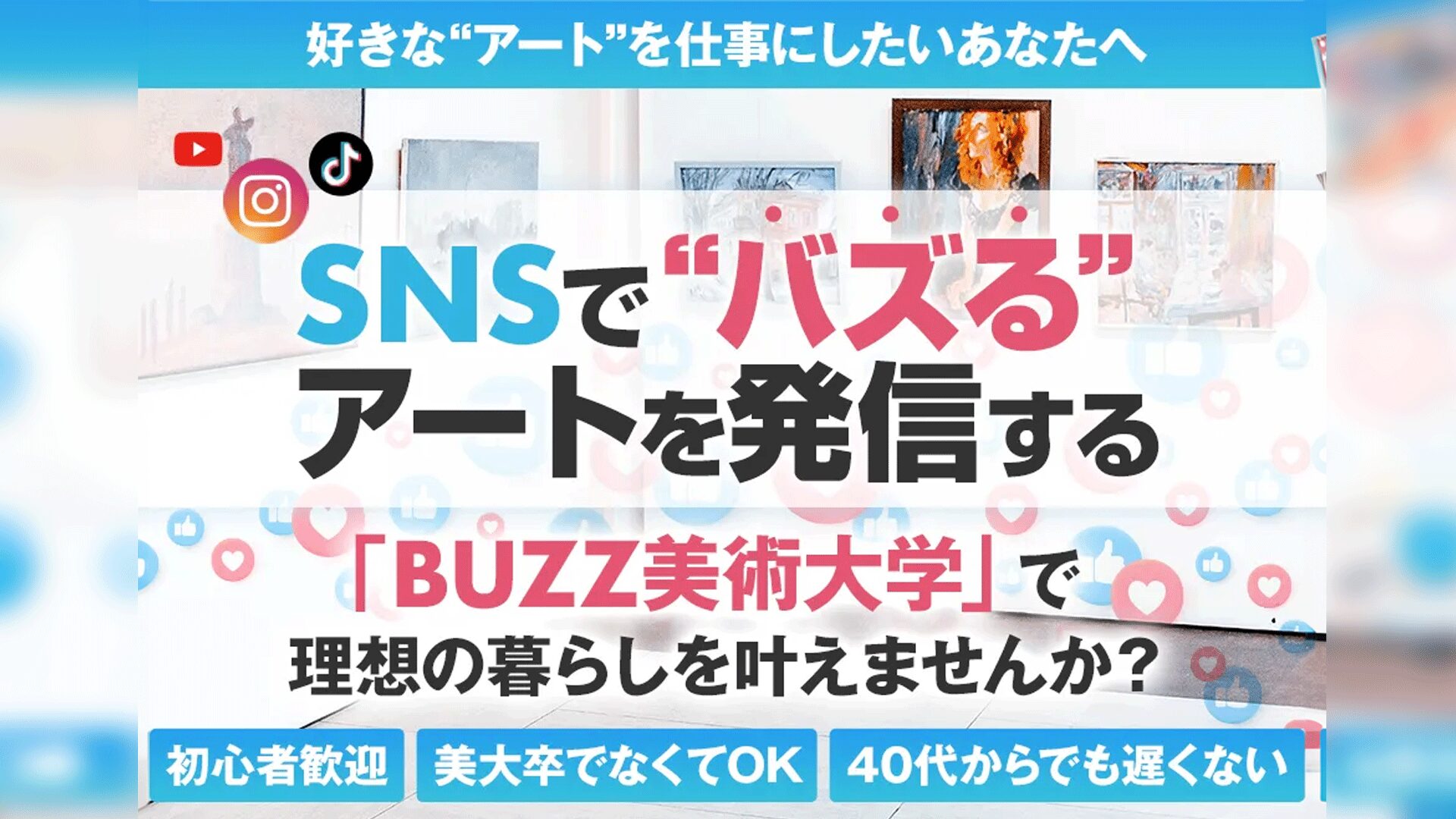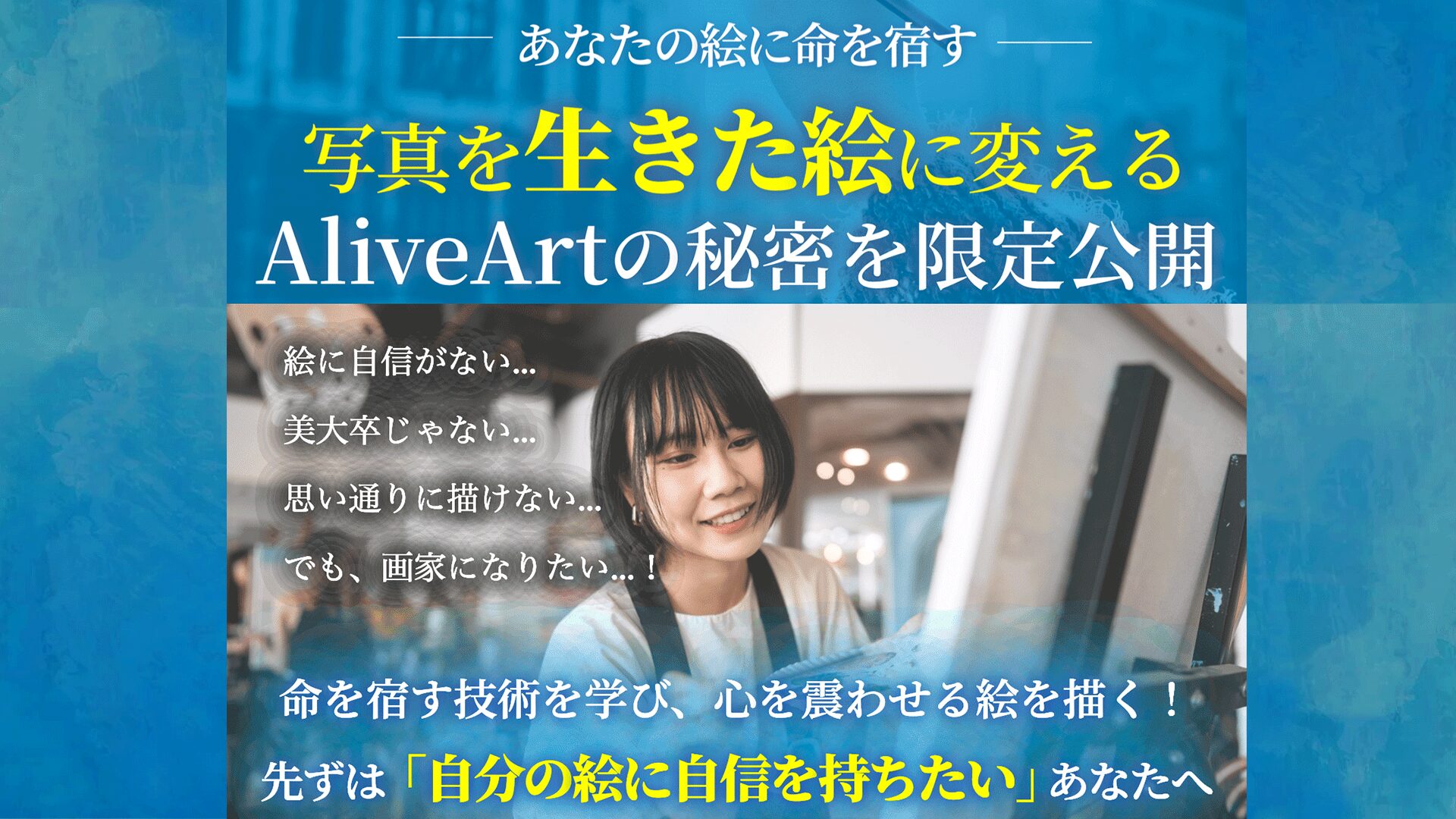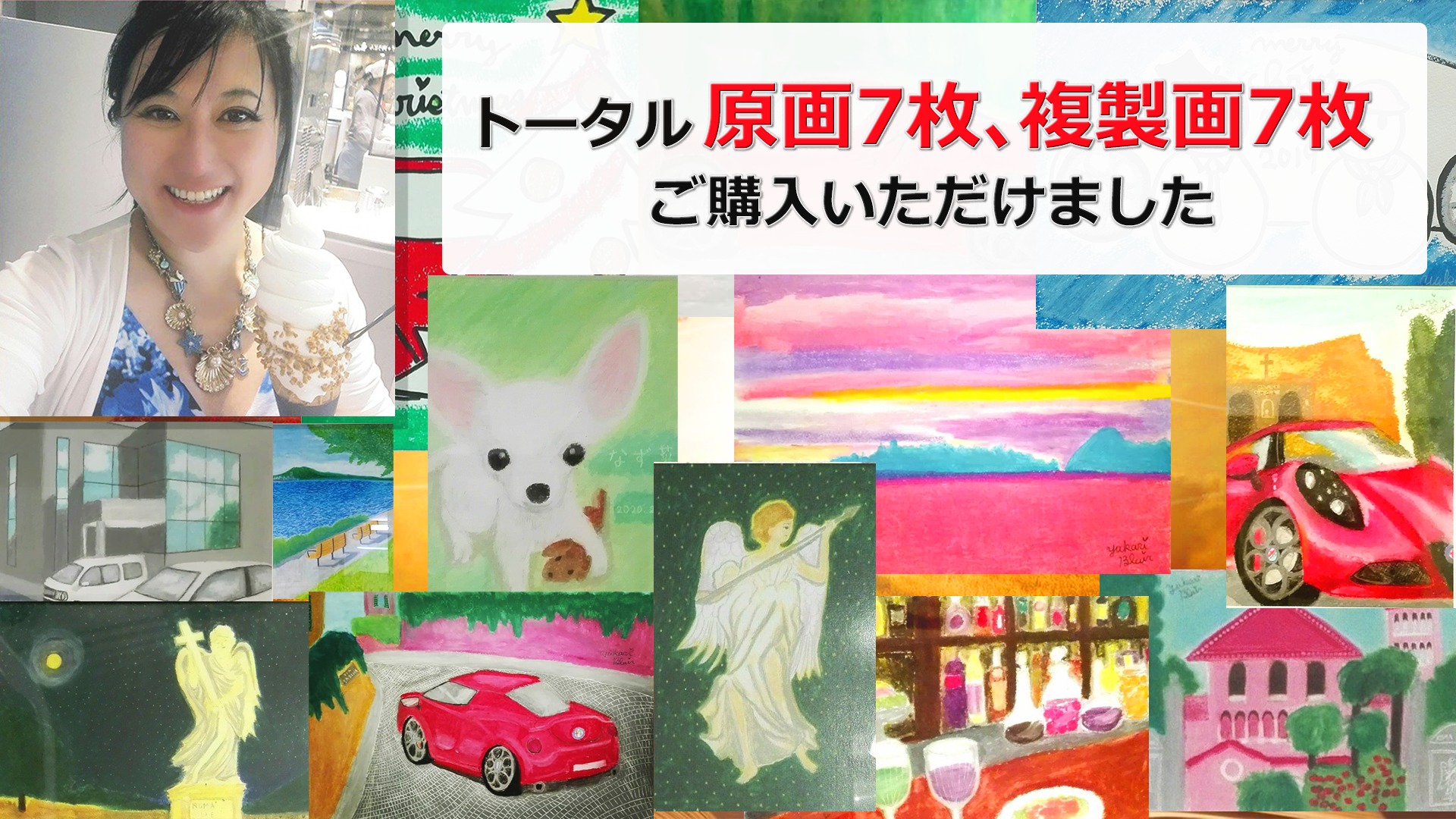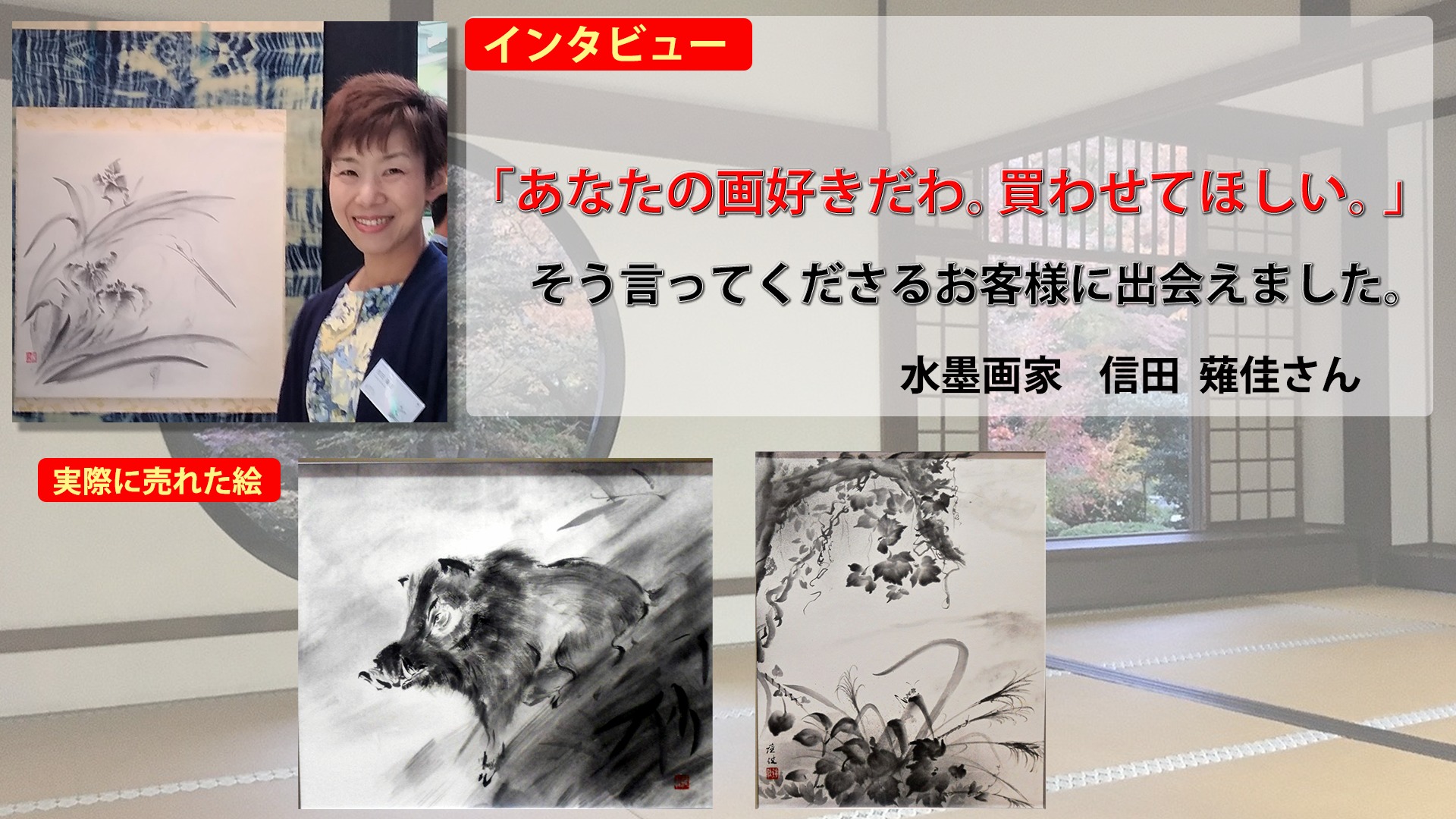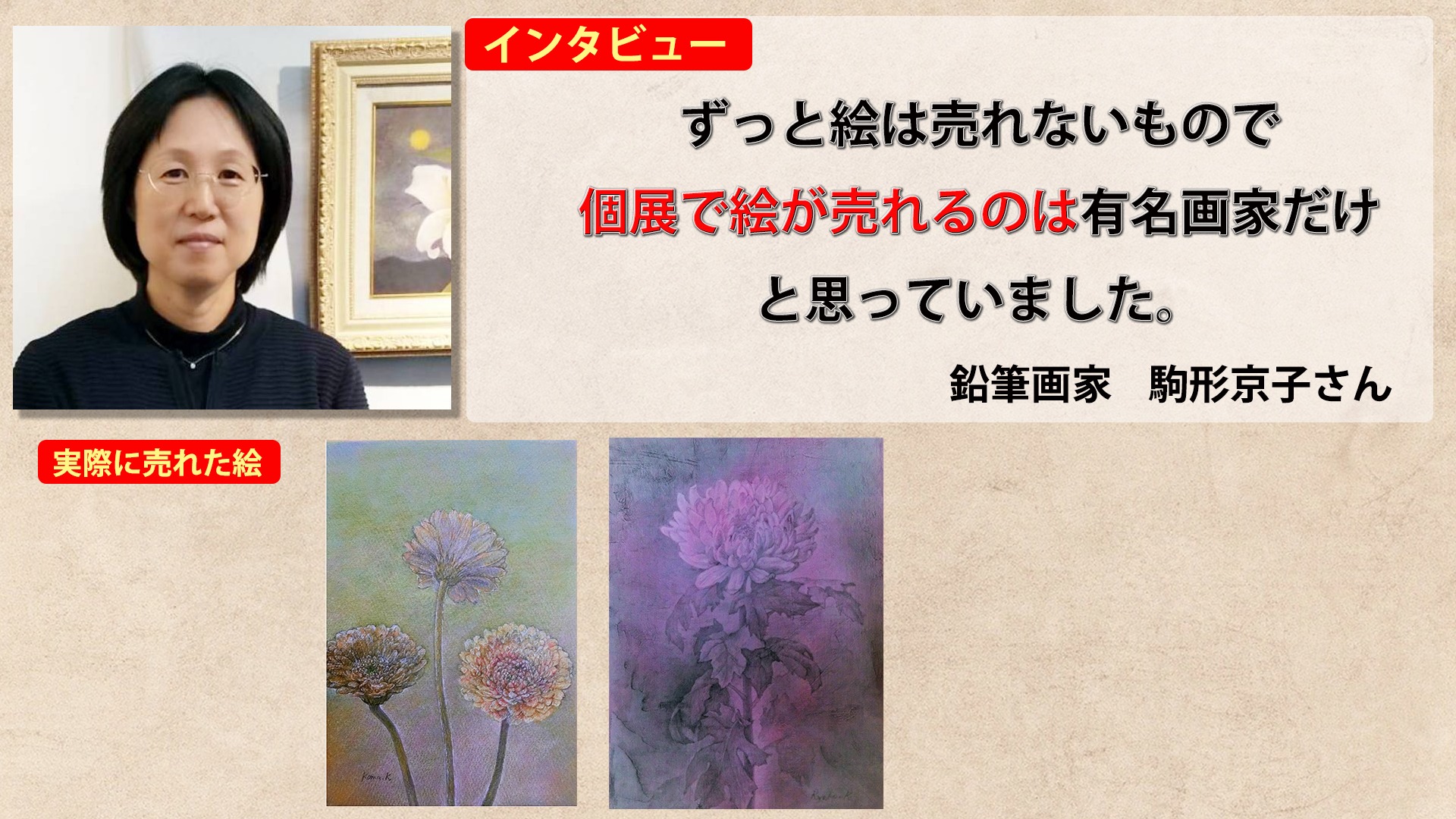どうも、最近イラストの仕事を頼まれて動揺している黒沼です。
実は私はじっくり描く緻密な絵画ばかり描いていたので、さらっと描くイラストは苦手なんです。
私の作品はコチラ
さて最近は続けて、西洋美術史シリーズを書いています。
美大に通う私が美術史の授業、教授の話、本で手に入れた美術史情報をアップしていくので、チェックしてみてくださいね!
今回は写実主義の美術について解説します!
当時の音楽とともにお楽しみください
スポンサーリンク
目次
写実主義とは
美術史は大きな流れをつかむとそれぞれの時代の特徴がよくわかるようになるので、ここらで復習しておきましょう。
バロック期のヴェルサイユ宮殿はルイ14世の豪華な趣味が反映されていました。↓

この高圧的な雰囲気に反発したロココは軽やかで女性的でした。↓

ロココの軽薄な雰囲気を嫌って、新古典主義では、不動の価値を古代ギリシャ・ローマにもとめました。↓


新古典主義の古代一筋な頑固さに反発し、ロマン主義では多様な美の価値を追い求め、異国情緒あふれる夢の中のような絵が描かれました。↓


ロマン主義の現実逃避的な性格に反発して登場したのが、写実主義でした。
写実主義は目の前の現実を描くことを重視しました。
そこで、モチーフは古代の神々でも、外国の風景でもなく、ありふれた人々が選ばれました。

モデルはマリア様や神様ではなく、労働者や農民になったんですね。
この時代に芸術=美しいという図式が崩れます。

聖書の中の美しい天使よりも、身の回りの労働者の姿の方が「リアル」に感じるわけです。

身の回りの現実をうつしとったので写実主義(レアリスム)なんです。
Mr.反骨精神 クールベ

写実主義(レアリスム)の最も有名な画家がクールベです。

クールベはまさにレアリスムらしい身の回りの労働者や、一般人の葬式などの卑近なモチーフを描きました。↑
クールベは様々な絵画のお約束を破壊していきます。
↓の絵は「画家のアトリエ」という絵画ですが、様々なモチーフがシンボルとして描かれています。

絵を無垢に見る子どもは理解のシンボル
絵の横にいるヌードモデルは自然のシンボル
などです。実はこのシンボルはクールベが自分で作ったルールなんです。
クールベ以前の絵画に使われたシンボルは誰が見てもわかるものでした。
例えば

頭の上の光輪は聖人のシンボル
十字架の杖と毛皮を持っているのは洗礼者ヨハネ
などです。
クールベの型破りな性格を物語るエピソードがあります。
「天使を描いてくれ」と言った依頼主に、クールベは「僕には天使が見えない!」と返事したそうです。
クールベはそれほどリアルにこだわったレアリスムの代表のような画家なんですね。
ゴッホも大好き ミレー

ミレーは農民を描き続けた画家でした。
それまでの絵画のモデルといえば、神々や英雄、英雄など誰にとっても立派なものでした。

ミレーは誰にとっても美しいものではなく、自分にとって美しいと思うものを描いたんですね。
ミレーの言葉に「美は表現である」というものがあります。

「日々の労働に勤しむ農民の姿こそ立派で美しい」というミレー個人の主張の表現がミレーの絵画なんですね。


後の時代の画家ゴッホはミレーのファンだったようで、多くの模写を残し、ミレーと同じ題材、場面の絵画を描いています。
スキャンダラスな男 マネ

マネも、クールベやミレー同様、絵画のお約束事を破壊した画家でした。

ルネサンス期の芸術家ミケランジェロ↑は「絵画は彫刻に近づくほど良いものになる」という言葉を残しています。
彫刻家であったミケランジェロらしい一言ですが、実際、古い時代の絵画はもともと彫刻の代わりに作られることも多かったんです。
聖人の彫像を作れない教会が代わりに聖人の絵画を注文するという感じです。
つまり、絵画はより立体的であるべき だったんです。
マネの絵はこの常識に挑戦しました。
↓正面から光の当たったモデルは平板に描かれています。

またこの絵画は女神でもない普通の女性が裸でこちらを見て挑発しています。
当時はワイザツだ!騒ぎになったようです。
↓の「草上の昼食」はさらにスキャンダラスでした。この絵はピクニックを楽しむ集団の中になぜか一人裸の女性がいます。

実はこの絵画はルネサンス期の画家ラファエロの女神を描いた版画のパロディーなんですが、モデルが一般人であることが物議をかもしました。

↑これの

↑この部分
それまでの絵画ではヌードを描く時は、女神像として描く というお約束がありました。
人間の裸はワイザツだけど、裸の女神像は自然の美しさの表現だったんですね。(すごい理屈ですね)

マンガもいけるくち ドーミエ

ドーミエは新聞の挿絵画家として活躍していました。

↑当時の世相を風刺したものが多く、新聞記者らしい率直な社会への観察眼を感じます。

絵画を見ても、やはり身の回りの人々のありのままの生活を描いています。
3等列車を描くあたり、さすが新聞記者です。ドーミエは庶民の味方だったんですね。
バルビゾン派って何ぞや?

ターナーやフリードリヒなどロマン主義の頃から、風景を主役とした絵画、風景画が描かれ始めました。
レアリスムの時代にも風景画の勢いは着々と強まり、印象派へと続いていきます。
レアリスムの時代、フォンテーヌブローの森の程近く、バルビゾン村で多くの画家が制作に打ち込みました。
この、何の変哲もない自然を切り取り描いた画家たちをバルビゾン派と呼びます。
・コロー

コローはバルビゾン派で最も有名な画家でしょう。
銀灰色の風景画と呼ばれる彼の絵画には清涼感があふれていますね。
それまで、風景は手早く描いたスケッチをアトリエに持ち帰り、スケッチを見て仕上げる
というスタイルで描かれました。
コローは毎日、現場へ通い、完成まで風景を見て描いたようです。
この制作スタイルは斬新だったようで、友人に「今日も君は永遠の下描きをやるのか」と冷やかされたようです。
この屋外で完成まで描くスタイルは印象派に受け継がれます。
・テオドール・ルソー

テオドール・ルソーのこの作品は日没という特定の時間をテーマにしていた点が斬新でした。
しかし、当時は評価に恵まれず、彼は4回連続で落選してしまったようです。
・ジュール・デュプレ

ジュール・デュプレもバルビゾン派の有名な画家で、多くの風景画を残しました。
テオドール・ルソーとは友人だったようです。
・ドービニー

樹木をメインに描く画家が多いバルビゾン派の中で、ドービニーはきらめく水面を主なモチーフにしました。
このモチーフは印象派に大きな影響を与えたようです。
・ディアズ

バルビゾン派の多くの画家が反アカデミズムでした。
それまでのアカデミズムの描き方では、褐色の絵の具を何層も重ねて立体的に描いていました。
しかし、ディアズは明るく鮮やかな色をパレットに作り、いきなりキャンバスに置くという描き方をしたようです。
この描き方は印象派のルノワールに大きな影響を与えたようで、筆触分割の元ネタになったようです。
まとめ

今回はレアリスム(写実主義)について取り上げました。
レアリスムの特徴はまとめると
・絵画の読み取り方を変えた
・画家個人の表現として絵を描いた
という感じですね。
身の回りのものから着想を得て、描くという今なら当たり前の発想方法はこの時代に生まれたんですね。
次回は印象派について紹介します。
それでは。
↓西洋美術史についてはコチラ↓