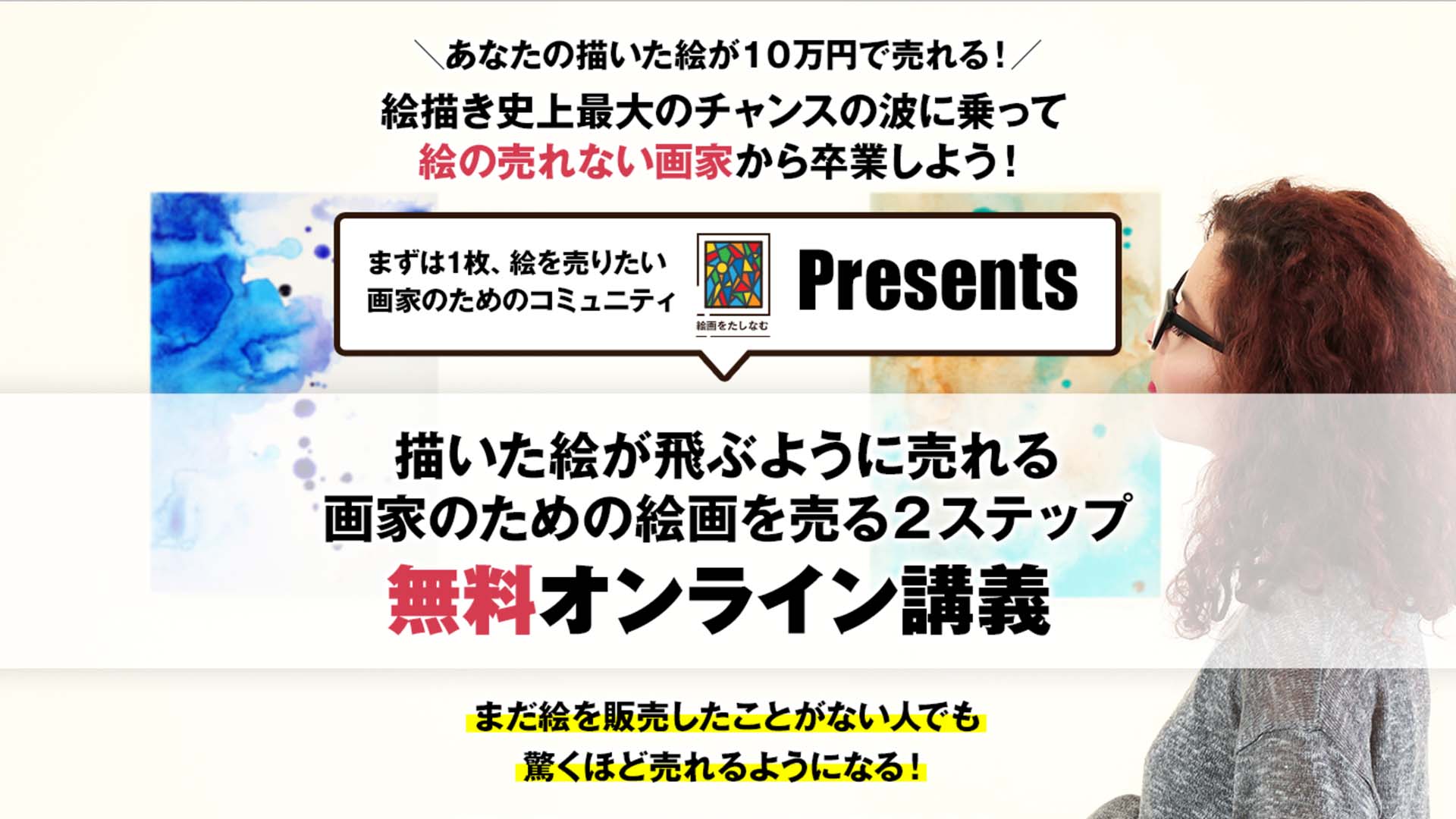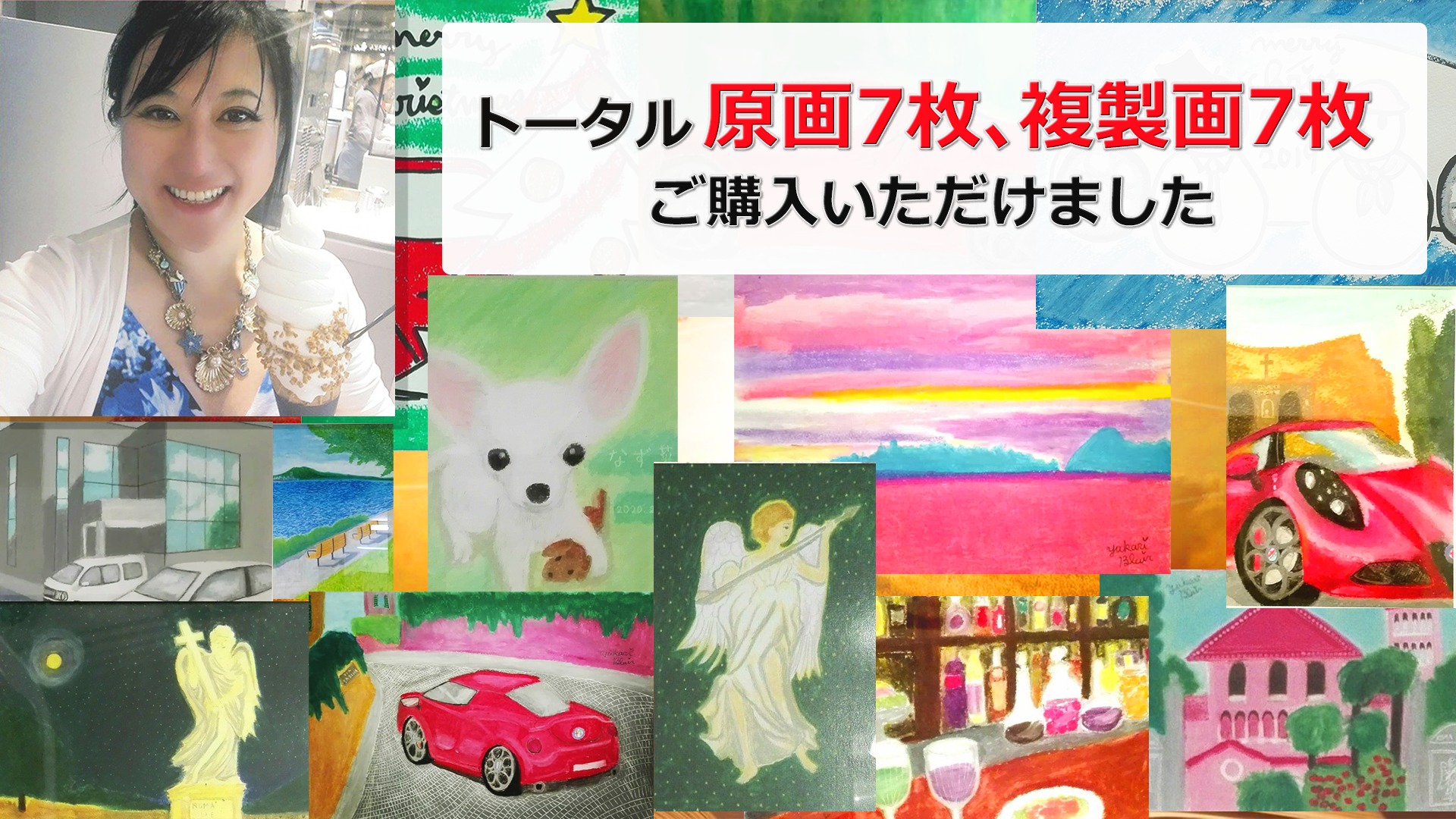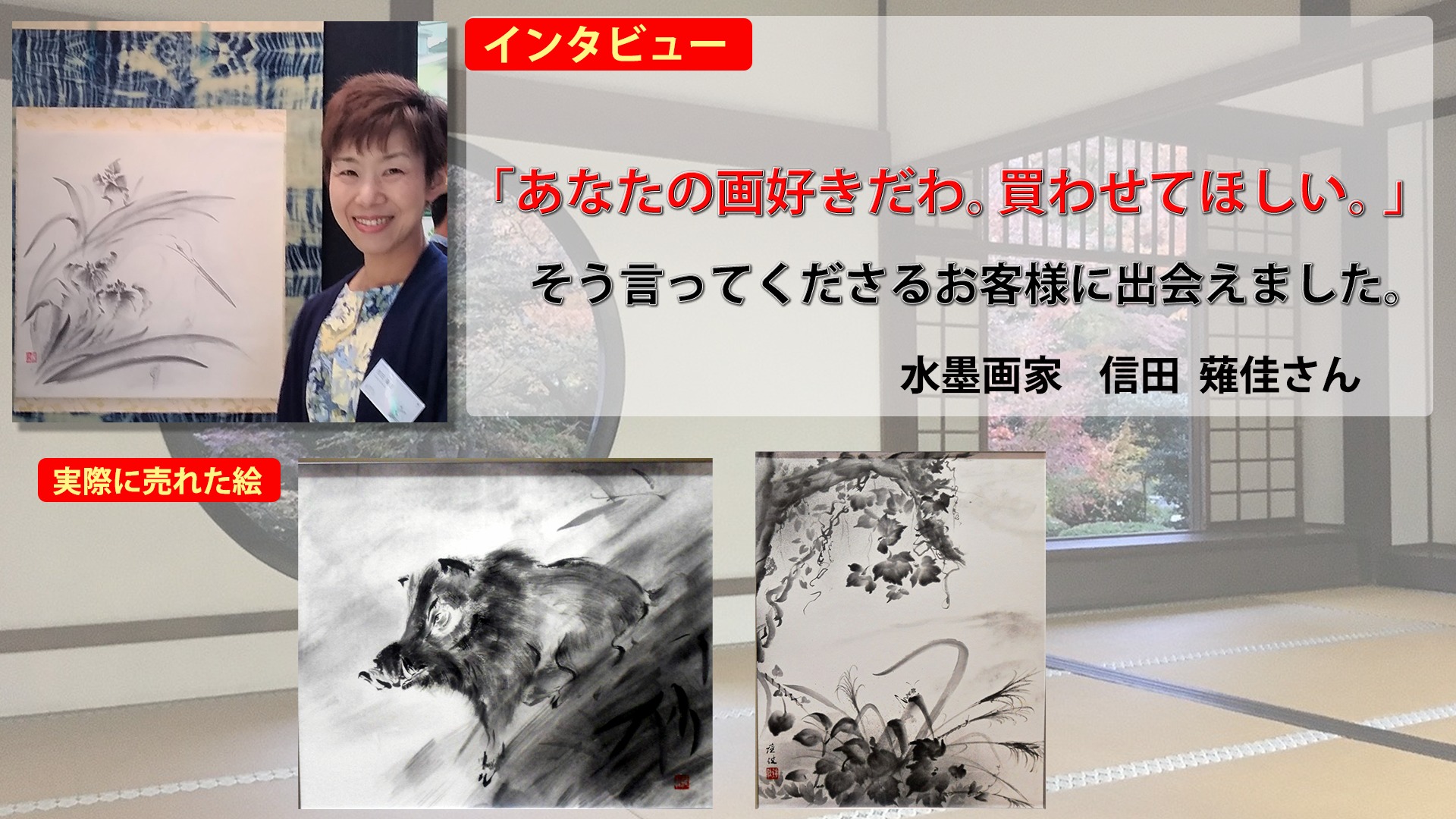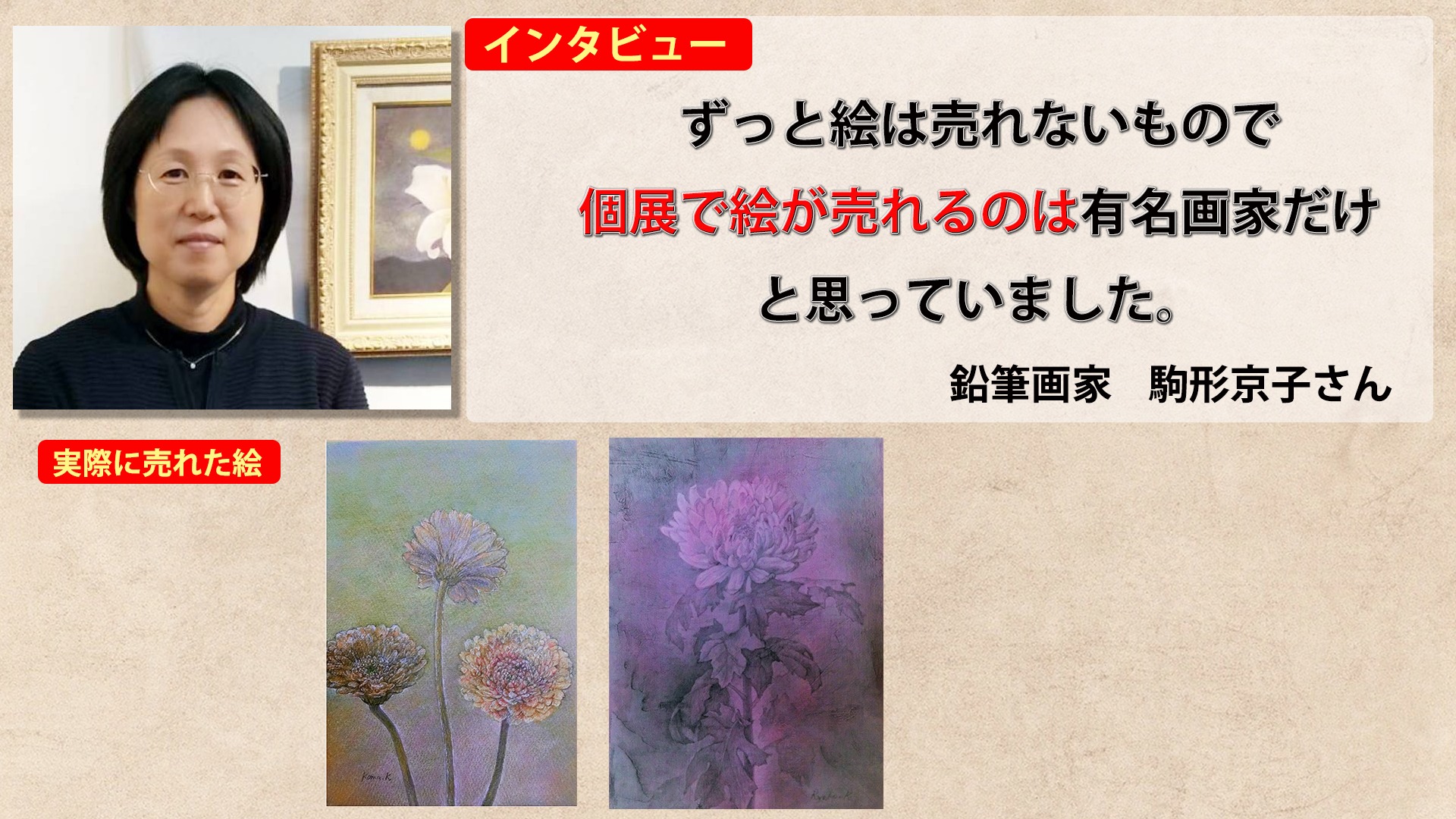絵の構図が悪いねぇ
修行時代、私はよくこんなことを
いわれていました。
この悩みに共感する方は多いかも
しれません。
絵を立体的にリアルに描くのは
得意でも、色彩や質感の再現が
得意でも、
構図が悪い
そんな方は多いものなんです。
また
まだ形狂ってるよ~
何度デッサンの形を修正しても
絵の先生にこう言われてしまい
やきもきする。
うーん光をかんじないなぁ。
もっと描写しなよ。
と講評の時に毎回言われる。
デッサンはできるけど
色を塗ると絵が平面的に
なっちゃう。
色感がなくて狙った色を
作れない。
こんな悩みを持っている方も
いるかと思います。
今回はこのような悩みを
全て解決していきます。
これらの悩みを解決する
絵の練習方法をいくつも
紹介するので是非最後まで
読んでみてください。
これまでは「絵を飾って楽しみたい」
「絵を観に行きたい」人むけに
記事を書いてみました。
今日は「絵を描きたい人」
「画家になりたい人」に向けた
記事を書いてみようと思います。
自己紹介の記事でも書いた通り、
私はなかなか絵が上達せず、
長い絵の修行時代を送りました。
そんな私が色んな方から教わった
「絵がうまくなる方法」について、
書いてみようと思います。
目次
絵を練習しても上達しない理由
絵の練習方法がよくわからん。
練習しても上達しない…
絵を上達させたい人、絵を描く
練習がしたい人で、そんな悩みを
持つ方は多いようです。
でも、なかなか絵が上達しない、
練習に練習を重ねても上手くならない
私もそんな絵が下手な人間でした。
ではそもそも、
「絵がうまく描けない理由」
って何なんでしょうか?
その理由はズバリ
「モチーフを十分に見れていないから」
「自分の絵を十分に見れていないから」
「線や色が選び抜かれていないから」
この3つだと言えます。
絵の練習で押さえるべきポイント
絵の構図が「上手い絵」はこの3つのポイント
を押さえて描かれた絵だと言えます。
つまり
「モチーフを十分に見れている」
「自分の絵を十分に見れている」
「線や色が選び抜かれている」
これが上手い絵の条件と言えそうです。
それでは一つずつ解説していきます。
「モチーフを十分に見れている」
物をリアルに描きたい場合、
このポイントが最も重要です。
モチーフを十分に見る とは
より具体的には、
モチーフの形、色、
モチーフに当たる光
を見るということです。
「自分の絵を十分に
見れている」
これはピンとこない方も
多いかもしれません。
「自分の絵を十分に見れている」
とは簡単に言えば、
絵の中でリアルに
みえるかどうかです。
より具体的に言えば、
実際のモチーフの色や形とは
違うけれども、
絵の中で適切な色や形が
選べている
ということです。
絵の練習方法その1:良い構図を探る練習
絵の練習方法について具体的に解説
していきます。
まず初めは構図から解説していきます。
構図とはモチーフの
切り取り方と配置の仕方です。
切り取り方(トリミング)は
おそらくイメージしやすいと
思います。
しかし「配置の仕方」は
どうでしょうか?
配置の仕方については少し
難しい話なので、具体例を
挙げて説明します。
モチーフの配置の仕方を
変えるだけで
自然で立体的な空間を
描きやすくなるのですが
2つのリンゴを描く場合、
自然な空間を演出する上で
良い形(設定)は
AとBのどちらでしょうか。
 A
A
 B
B
Aは2つのリンゴの
輪郭が点で接しているため、
平面的な模様のように
見えるかと思います。
つまり、どちらのリンゴが手前に
あるのかすぐに分かりませんね。
これに対しBは2つのリンゴが
少し重なっています。
どちらのリンゴが手前に
あるのかすぐにわかりますね。
とても些細なことに思えますが、
絵の中でどちらの設定を選ぶかで、
自然な印象に見えるか
どうかかわってくるのです。
モチーフの配置の仕方を
を学ぶ練習方法をいくつか
紹介おきます。
名画の配置から学ぶ

モチーフの配置の仕方や
重なり方の良い例は
名画、特に静物画の名画の
構図を研究すると良いでしょう。
今回はいくつか参考になる
静物画の名手を紹介しておきます。
17世紀オランダ絵画


フェルメールが生きたのと同じ
17世紀のオランダにはこのような
緻密でリアルな静物画を描く画家が
たくさんいました。
この時代の静物画はリアルな描写力
に目を奪われますが、彼等の作品は
構図もとても参考になります。
この時代はオランダ絵画の黄金時代
といわれており、突出した才能を
持つ画家が本当にたくさんいたのです。
20世紀、色彩の天才といわれた
マティスも修業時代にこの時代の名画
から構図を学んでいたようです。
シャルダン



シャルダンはロココ期の画家で
庶民の質素な暮らしを感じさせる
素朴なモチーフを高い描写力で
描いた画家です。
質素な料理や狩りの獲物など
なんてことないモチーフが
高い描写力と引いた構図の演出力
のおかげで
神秘的でありがたいものに
見えてきますね。
17世紀オランダ絵画よりは少ない
要素で画面を構成し描いているのも
注目すべきポイントだと思います。
アンリ・ファンタン・ラ・トゥール



ここまでは古典絵画にありがちな
暗闇の中にスポットライトが
当たっていて
黒バックのなかでモチーフが
描かれている
そんな空間の静物画ばかりでしたが
彼の作品は生活のワンシーンを
切り取ったような自然なライティング
で描かれたものばかりです。
シャルダンの作品よりもモチーフは
少なく、劇的な光の設定ではないので
上品で静かな雰囲気が漂っていますね。
モランディ


モランディは20世紀の画家なので
かなりモダンな印象の作品ですね。
モチーフの立体感や象徴的な意味合い
はそぎ落とされ、純粋な色面を画面上で
構成して絵を作る
そんな意識で描かれています。
彼の作品は意図的に立体感を
つぶすための配置の仕方をしている
ものもあるため注意が必要ですが
↑に紹介したものは光を設定して
立体的に描写するまでもなく
モチーフの前後感を感じるような
配置を選び抜いたものになっている
ので参考になると思います。
絵の構図を考える上で
リアルに物を描く上で
「色の配置が選び抜かれている」
これも重要なポイントなんです。
色に関しても選び抜くことは重要なんです。

これはポスト印象派の画家、
ゴーギャンの作品ですが、
とても地味な色ばかりが使われています。
しかし、色の組み合わせが
選び抜かれているおかげで、
全体として調和しており、
統一した雰囲気を演出できています。

こちらはゴーギャンの同じ作品を
モノクロにしたものですが、
白、明るいグレー、暗いグレー、黒
など、モノトーンにしても
バランスよく色が配置されていることが
わかりますね。
このように、様々な色を使った
名画でもモノクロで見ると
様々な明るさの色が豊かに
配置されているものなんです。
絵の構図を練習する方法で
最もメジャーな模写は
見習いの画家が、親方(師匠)
の描いた絵画を同じ構図で
再現するという練習です。
この練習方法では
「自分の絵を十分に見れている」
という力をつけることができます。
巨匠たちの良い構図、良いモチーフ設定
を模写を通して、
手に覚え込ませる練習方法です。
これをすることで、自分で絵を描いた時も、
より良い構図、より良いモチーフ設定で
描くことができます。
「絵の中でのリアルさ」を演出する力
がつくわけです。
当時の見習い画家たちは、師匠の名画を
模写することを許可され、
その模写を売って生活費を稼いでいたようです。
模写には絵の上達以外の目的もあったんですね。

この作品は「プラドのモナリザ」と呼ばれています。

レオナルド・ダ・ヴィンチが描いた
『モナリザ』を弟子が模写した作品
のようで、
プラド美術館に所蔵されているため
こう呼ばれています。
絵の構図模写はザックリで良い


絵の構図を学ぶに模写をすべし。
そんな話をここまでしてきましたが、
名画の模写を細部まで完璧にやっていたら
いくら時間があっても足りません。
絵の構図を学ぶ上では、大まかな
絵の色と形を写し取る練習が重要です。
上の画像のように、名画の大まかな
色と形の配置を写し取る練習を
何枚も繰り返すことで
構図のセンスは磨かれていきます。
絵の構図を学ぶには抽象画もおすすめ

絵の構図を学ぶには抽象画もおすすめ
です。
抽象画は具象絵画から、色と形の
エッセンスのみを抽出したものです。
なので、具象絵画の模写に慣れてきたら
抽象画の構図を模写で学ぶのも良いでしょう。
抽象画の成り立ちや構図の考え方については
こちらの動画で解説しているので、
是非チェックしてみてください。
絵の構図を学ぶには半抽象画もおすすめ

絵の構図を学ぶには
半抽象画もおすすめです。
いきなり抽象画の模写をしても、練習に
ならなそうな場合は、モランディのような
半抽象の絵画を模写するのも
良いかもしれません。
このような絵画は、立体感や
モチーフの質感こそ
再現されていませんが
構図、つまり色と形の配置
は徹底的に選び抜かれているもの
なんです。

モランディ以外にも熊谷守一
の作品も構図の勉強には
とても役立つと思います。
半抽象画は、一見
誰にでも描けそうな
下手な絵に見えるかもしれませんが
実際に模写してみると
かなり入念に色と形が選ばれている
ことに気がつくものなんです。
絵の構図を学べるおすすめ本

絵の構図を学ぶのにおすすめの本を
何冊か紹介しておきます。
秀和システム
売り上げランキング: 23,274
絵画の構図を学ぶのにも
とても役だちます。
巨匠に学ぶ構図の基本―名画はなぜ名画なのか? (リトルキュレーターシリーズ)
視覚デザイン研究所
売り上げランキング: 49,987
売り上げランキング: 4,220
こちらは写真の構図の本です。
写真の場合は絵画とは違い
モチーフの配置を自由に変えることは
できませんが
良い切り取り方を学ぶ上で
役立つでしょう。
ドローイングレッスン -古典に学ぶリアリズム表現法- ハードカバー
ボーンデジタル (2012-07-22)
売り上げランキング: 186,136
こちらはデッサン全般をアカデミック
に解説した本ですが、
序盤に構図のパートがあり
とても重宝します。
豊富なカラー図版とともに
とても理論的、実証的に構図を解説した
おすすめの一冊です。
絵の構図の練習方法
絵の構図の効果的な練習方法として
おすすめしたいのが3色模写です。
ここまで紹介したような
名画を白黒グレーの3色だけで
模写するのです。
この3色模写については
練習方法を動画で解説しているので
是非チェックしてみてください↓
絵の練習方法その2:線で自然な形をとらえる
絵の練習方法で多くの方が悩むのが
「どうやって形をとれるようになるか?」
かと思います。
リアルに物を描く上で
「線が選び抜かれている」
これは重要なポイントなんです。
 A
A
 B
B
2枚のデッサンを見てどちらが
よりウマイと思うでしょうか?
Aのデッサンは輪郭線が選び
抜かれておらず、太い ですね。
また、Aは短い線がたくさん
集まって、太い線になっています。
Bは選び抜かれた長い線が
引かれています。
Aはとても味のあるデッサンですね。
でもよりウマイものを選ぶとすればBでしょう。
ちなみにBはナポレオンの肖像も
手掛けた新古典主義の画家アングルの
デッサンです。
彼はとても選び抜かれた線で
リアルに描くのが得意な画家でした。

線で形をとらえる具体的な練習方法
を紹介します。
今回は昔の画家が修行時代に
とっていた絵の練習方法を
紹介しようと思います。
近代以前、画家が職人であった
時代において
「リアルに描く」ことは
とても重要でした。
彼らの練習方法を知ることで、
絵の上達や、そのための練習に
役立てようというわけです。
今回紹介した上手い絵の3つの条件は
いずれも
「3次元のモチーフを
2次元平面に変換する」
ためのものです。
この課題をクリアするため、
昔の画家の見習いたちは
「クロッキー」と「模写」で
練習していました。
クロッキーとは、比較的短い時間で
書かれた「線」中心の絵のことです。

線と少しのグラデーションだけで、
モチーフの形を捉える
というのがクロッキーの目的です。
この練習方法では
「モチーフを十分に見れている」
「線や色が選び抜かれている」
という2つの力をつけることができます。
私は修行時代、このクロッキーを
1枚3分で1日20枚
という感じで決めて練習していました。
線で形をとらえる絵の練習方法
クロッキー
絵の練習方法として初心者に最もおすすめ
なのが、クロッキーです。
クロッキーとは短い時間(数分間)で
一筆書きでモチーフの形をとらえる
練習方法です。
こちらの練習方法も動画で解説しているので
是非チェックしてみてください。
ブロックイン
自然な形をとるための絵の練習方法
として、クロッキーと併せておすすめ
したいのが
ブロックインです。
ブロックインは絵を描きだす時に
大まかにモチーフの形や絵の構図を
長めの直線で探るテクニックです。
こちらも練習方法を動画で解説しているので
是非チェックしてみてください。
絵の練習方法その3:面で自然な明暗をとらえる
絵の練習方法について、ここまで
構図と形について解説してきました。
最後に紹介するのは色(明度)です。
構図、形、明度
この3つをコントロールできるように
なれば、
デッサン的な意味ではモチーフを
リアルに描けるようになります。
ここではモチーフの明暗を素早く
とらえられるようになる練習方法
面でとらえるクロッキーを紹介
します。
この練習方法のポイントは
明暗の境界線(稜線)の位置を
素早く見つけ出し
明暗を塗りわけるということです。
この絵の練習方法も動画で
解説しているので
是非チェックしてみてください。
絵の練習方法その4:細密デッサン
絵の練習方法について
ここまで構図、形、明暗の3つのテーマで
解説してきました。
この3つをしっかり描けるように
なっていれば、大概の物は
リアルに描くことが出来るでしょう。
ここでは細密描写の練習方法について
紹介しますが、構図、形、明暗をしっかり
描けるようになっていれば
細密描写はかなり機械的な作業で
時間をかければかけるほど
絵のクオリティーが上がっていくような
「作業」になります。
こちらのパートも動画で解説しているので
是非チェックしてみてください。
絵の練習方法その5:暖色と寒色で描く
絵の練習方法について
ここまで解説してきましたが
ここまではデッサンでリアルに物を
描く方法、つまりモノクロで絵を描く
練習方法でした。
ここからは、効果的に色を使って
物をリアルに描く方法を解説していきます。
まず最初に紹介したい色彩計画が
暖色×寒色による描写です。
モチーフの明るい部分を暖色系で描き
暗い部分を寒色系で描くと
劇的な光を感じる絵を描けるのです。
よく、デッサンは得意だけど
色を塗った瞬間に立体感がなくなって
しまう、色が選べない方がいますが
色はセンスで選ぶ必要はないのです。
科学敵に正しい効果的な使い方を
すれば
色で光を描くこともできるのです。
こちらも練習方法を
動画で解説しているので
是非チェックしてみてください。
絵の練習方法その6:隣り合った色相で描く
絵の練習方法のおすすめメニューは
まだまだあります。
先ほどの色彩計画、暖色×寒色で描く
では劇的な光を色の力で演出する方法
を解説しました。
お次は自然で雰囲気のある光を演出
する色彩の使い方を紹介します。
黄色、オレンジ、赤のように
隣り合った色相で画面を組み立てると
雰囲気のある自然な光を描くことが
できます。
こちらも練習方法を
動画で解説しているので
是非チェックしてみてください。
絵の練習方法その7:カラフルなモチーフを描く
絵の練習方法についていろいろ
紹介してきましたが
おそらくこの練習課題が最も難しい
かと思います。
しかし、ここまで解説してきた
構図、形、明暗、細密描写、暖色×寒色、
隣り合った色相
これら全てを理解しマスターしていれば
この課題もクリアできるでしょう。
この課題はカラフルなモチーフを
立体的に描くための練習方法です。
絵の専門家でも誤解している方が
時々いるのですが、
色鮮やかさと立体感は
正しい色彩理論を知っていれば
両立できるのです。
モチーフの色数がいくら増えようと
これは関係ありません。
こちらも動画で解説しているので
是非チェックしてみてください。
絵の練習方法その8:狙った色を作る
絵の練習方法についてここまでは
「描き方」にフォーカスして
解説してきました。
しかし、実際にカラーで絵を描くときは
常に欲しい色をパレット上で作る必要が
あります。
ここでは、狙った色を最短最速で
作る方法を解説していきます。
基本は↑の方法で、
どんな色でも作れるのですが
いくつか初心者がつまずきやすい
色の作り方があるので
ここではピンポイントで
解説していきます。
グレーの作り方
絵の初心者がまず覚えるべきなのが
グレーの作り方です。
狙った明るさのグレーを作ることが
できると
画面上で鮮やかさを自在にコントロール
できるようになります。
多くの場合、人は狙った色よりも
やや鮮やかにやや暗めに色を
作ってしまいます。
そしてその色を塗った結果
画面上で明暗の関係や彩度の関係が壊れ
立体感を損なうのです。
そんな時はグレーを混ぜて、
明度や彩度を微調整しましょう。
こちらも動画で解説しているので
是非チェックしてみてください。
茶色の作り方
これは非常に不思議なことなんですが
絵の初心者には
茶色の作り方がわからない方が
多いのです。
結論から言えば、
茶色は暗いオレンジです。
こちらも動画で解説しているので
是非チェックしてみてください。
明るい緑と赤の作り方
こちらは中級者、上級者でも知らない
方がいるのですが
明るい緑や明るい赤を自然に
絵の中で使うには
ちょっとした工夫が必要なのです。
こちらも動画で解説しているので
是非チェックしてみてください。
絵は練習で上達するのか?

絵の練習方法について、ここまで
理論の部分をおおまかに
解説してきました。
しかし、実際にうまい絵
を描けるようになるのには
多くの練習が必要です。
しかし、中には初めから
構図のセンスが良く
最初から良い構図で
絵を描けたり、形を描けたり
する人もいます。
でも、だからといって
「私はセンスないなぁ。」
と落ち込むことはありません。
多くの場合、構図や形のセンスが
ある人は色彩感覚に弱点があるかた
が多いものなんです。
形派か色派かといった感じで、
色派の人は構図選びが苦手な
人が多いようです。
漫画家には構図や形が得意でも
色が苦手という典型的な形派の人が
結構います。
(まあ、色も形も最初からバッチリ
な人もたまにいますが笑)
構図が苦手な人は良い構図の絵を
マネしまくることで、センスを磨く
ことができるようになります。
形が苦手な人はクロッキーを
何百枚と描けば上達します。
明暗を見るのが苦手な方は
写真を使ってコンテで模写して
みましょう。
まとめ

今回は絵の上達方法、
デッサンや着彩の練習方法
について解説しました。
巨匠たちも地道な絵の練習して
上達していったんですね。
それでは今日はこのへんで